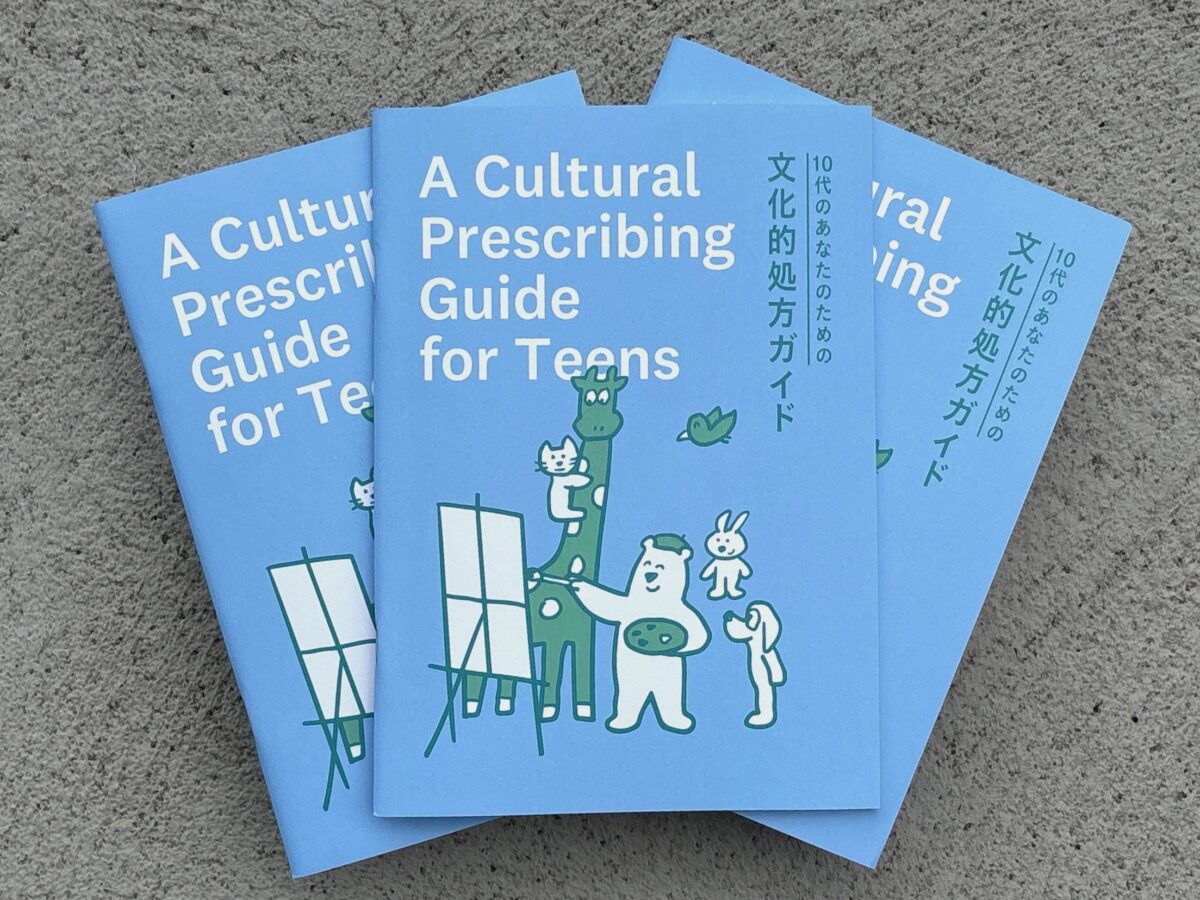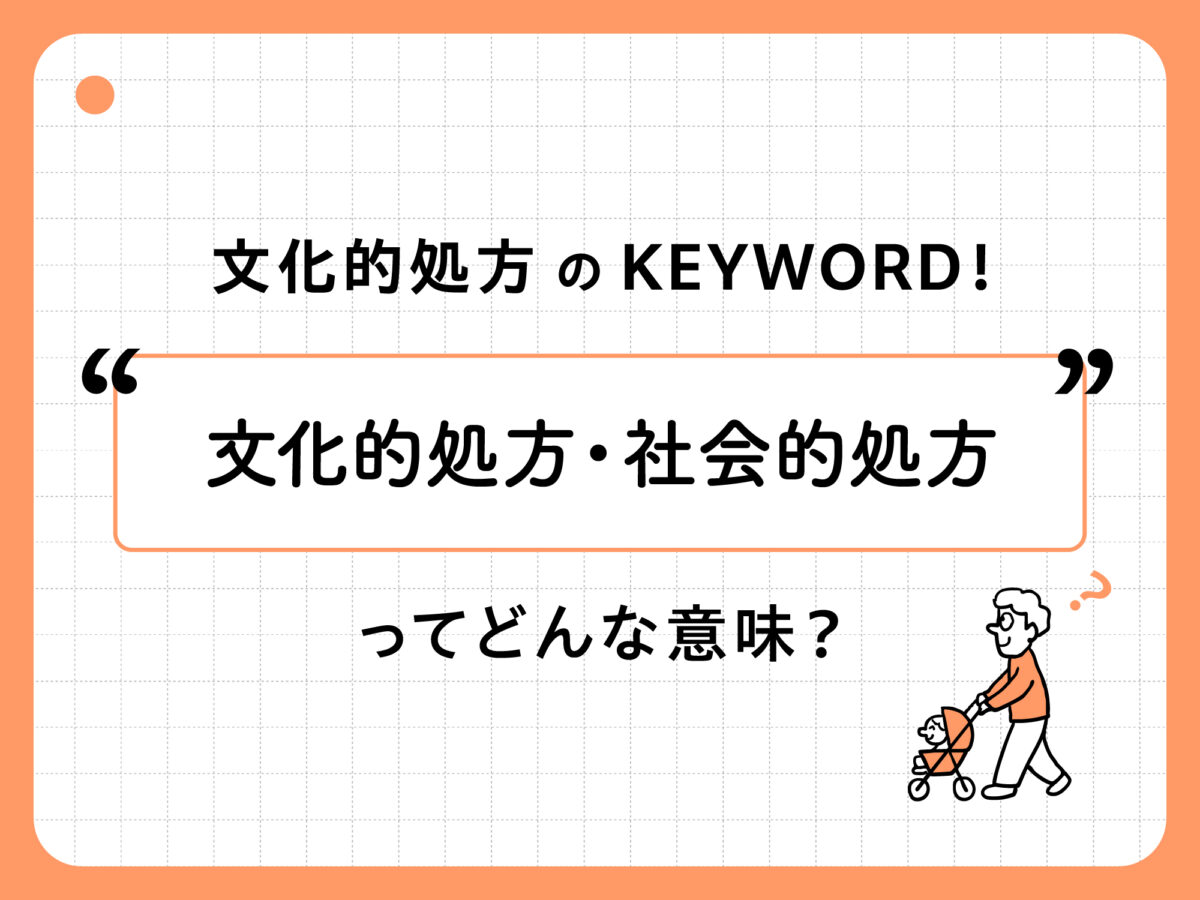 文化的処方のKEYWORD!”文化的処方””社会的処方”ってどんな意味?
文化的処方のKEYWORD!”文化的処方””社会的処方”ってどんな意味?東京のTIBで開催された文部科学省主催の万博のイベント「わたしとみらい、つながるサイエンス展」。その中で行われた展示「文化的処方を体験しよう!Hello Future!」では、専門人材「文化リンクワーカー」による「おしゃべり鑑賞会」や、音楽家・古川聖さん(東京藝術大学教授)による参加型音楽体験「空間楽器・ミュージッキング」が注目を集めました。人と人、人と社会をアートでつなぐ文化的処方ワークショップをレポートします。

アートを介して人と人をつなぐ「文化的処方」

「文化的処方を体験しよう!Hello Future! 100年ミュージアム」の展示では望まない孤独や孤立の解決策としてアートや文化を介して社会の中でのつながりを創出する「文化的処方」という仕組みの提案をしています。会場では画家の上田薫さんの絵画やアーティストの日比野克彦さんの作品が展示されていました。また、作家の子どもの頃からのアルバム写真や川崎市の市民が撮影した市街の風景をとらえた写真も展示されています。写真パネルは手に取ることができ、それをモニターの前に置くと関連動画や情報が映し出されます。

「川崎市・市民コンクールの作品より」と題された展示は、デジタル技術によって保存・再生された市民の視点による川崎の記録です。地域の記憶を共有することで世代間のつながりを促す「文化的処方」の実践例となっていました。作品を見ている来場者に積極的に話しかけている人たちがいます。文化リンクワーカー「ああとも」です。

文化リンクワーカーとは、アートを通じて人々の社会的つながりやウェルビーイング(心の健康や幸福感)を高める専門人材のこと。ああともは、専門的な知識を一方的に伝えるのではなく、来場者が自らの感覚や体験を語り合う「おしゃべり鑑賞会」を実施しました。しかし、来場者の多くは文化リンクワーカーの存在を知りません。話しかけられて少し驚いたような人もいましたが、すぐに談笑をしたり、互いに作品についての感想を話していました。ああとものコミュニケーション能力の高さに驚かされます。文化リンクワーカーは来場者自身の視点や感性を引き出し、作品への新たな気づきを促していました。

「まずは来場者の興味を探りながら対話をします。アートを難しい、高尚なものと感じている方もいますが、対話を通じてそうした壁を越えていくことを目指しています」と、ああともの財津さんは笑顔でそう語ります。おもしろいのは、会話のきっかけは「アート」ではないことも多々あるということです。ある親子は、特にアートにも文化的処方についても興味はありませんでした。しかし、写真パネルに使用されていたNFC(近距離無線通信技術)タグの話題から、来場者の趣味の鉄道の話題で盛り上がりました。NFCタグは交通系ICカードに使用されている技術です。「へえ、そうなんだ!」。来場者の男の子の目がキラリと光ります。身近な話題をきっかけに、アートとの距離がぐっと縮まった瞬間でした。

ここで行われる「おしゃべり鑑賞会」は対象をじっくり見ながら、何人かで言葉を重ねていくオブジェクト・ベースド・ラーニング(OBL)と呼ばれる観察方法を取り入れています。「知識は共同的に構築されるもの」という考え方を基盤としており、ひとりの視点ではなく、複数人の見方が重なり合わせることに妙味があります。思考のレバレッジ(てこ)のように、見えている作品の世界が違って見えるのです。文化リンクワーカーああともの活動は、対話を通じて、一人で見る以上の面白さや気づきを与え、その経験を家族や友人に伝えることでさらに文化的なつながりを広げることを目的としています。

会場の隅にはカラフルな屏風状のパネルが置かれています。作品を見た人たちが足を止め、「100年後に遺したいもの」「気になった作品」を言葉にして、パネルに貼り付けていました。参加者の言葉は会場に掲示され、世代を超えた交流の場となりました。財津さんはOBLでの作品鑑賞の面白さを「同じ作品を見ながら対話することで上下関係のない、フラットな関係性が生まれること」と言います。
「空間楽器・ミュージッキング」が創り出す音の彫刻
ステージ上では古川聖さんによる「空間楽器・ミュージッキング」のワークショップが開催されました。参加者はスマートフォンでQRコードを読み取ることで、手軽に音楽演奏に参加することができます。専門知識や演奏技術は不要で、QRコードを読み取ったスマホが即席の楽器となり、音を奏でるのです。

この日、「モーツァルトを弾いてみる」と題したパフォーマンスが行われました。演奏するのは親しみやすい第一楽章のメロディが有名な『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』。参加者にはバイオリン(第1、第2)、ビオラ、チェロ、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットというパートが振り分けられます。本来は弦楽合奏ですが、木管楽器が加えられるアレンジがされています。

冒頭は力強いユニゾンで始まり、第1バイオリンが主旋律を弾むように奏でます。そして、それぞれの楽器も自分のパートを演奏していきます。
「自分のパートの楽器はこんな音を出しているのか」。まるで、自分が楽団にいるような気持ちになります。初めての体験に戸惑っていた参加者の顔も次第に笑顔になり、自然と交流が生まれていました。スマートフォンを傾けることで音量が変わるので、参加者は自分自身が楽器を奏でているような感覚になります。初めて会った人たちなのに、音楽によって会場が一体となりました。

「この仕組みを『空間楽器』と呼んでいます。最初はたくさんの音源を自由に動かして空間に大きな音の彫刻を作ろうと思ったんです。それをやっているうちに、バラバラの成分(音)で音楽をやってみたら面白いんじゃないかと思い、このような形になっていったんです」と古川さんが説明してくれました。
たしかに、自分が担当する音の「成分」を認知すると、自分と音楽の関係がより深まったような気持ちになりました。「そう、『これとこれが合ってる、組み合わさってる!』みたいに、音と自分の関係を認知するとおもしろいですよね」と古川さんは微笑みます。

「今、社会は大きく変わり、アーティスト像というのも変わると思いますね。近代が作った『孤高の天才』のような神話に包まれたアーティスト像はもう時代に合わないのでしょう。むしろ、人と人の関係の中から生まれていくアートの形があり、それを日比野さんなども実践していますよね。私自身も、みんなが楽しめる作品を作ることに満足を感じています。もちろん一方で、わかりにくい現代音楽も制作していますが(笑)」

古川さんは『空間楽器』によって、音楽に馴染みのない人でも簡単に参加できる空間を創り出しました。「空間楽器」のシステムは原理的には何百人、何千人という規模でも実現可能だといいます。将来的には野球場のような大空間でも実施できる可能性があるそうです。

文化的処方がもたらす可能性
このイベントでは専門家から一方的に知識を伝えるのではなく、参加者が主役となる双方向の体験を通じて人とのつながりを深めていました。文化的処方とは、芸術体験を通じて誰もが持つ社会とのつながりに気づき、心身の健康や孤独感の解消、コミュニティ再構築を目指す考え方です。文化リンクワーカーが実践するOBLの「おしゃべり鑑賞会」と古川さんの「空間楽器・ミュージッキング」はどちらも、アートを介して人と人の関係性を構築する文化的処方の実践例です。こうしたアートや音楽の体験が社会に浸透することで、より包摂的で創造性豊かな社会をつくる可能性が広がります。今回の展示は、その可能性を多くの人に示す機会となりました。