ああともについて

プロジェクトの概要
Art & Wellbeing「ああとも」(以下、ああとも)は、国立アートリサーチセンターと東京藝術大学が連携して推進する「アートとウェルビーイング(心身の健康)」をテーマにしたプロジェクトです。アートや文化資源を介して心身の健康を促す「文化的処方」を、美術館など文化拠点機能を活かしながら、地方自治体と連携し実践を進めています。このプロジェクトは東京藝術大学を拠点に、大学、国立美術館などミュージアム、地方自治体、民間企業など産官学の41組織(2025年6月現在)が連携する「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点」事業の一環として取り組んでいます。
私たちの目的
近年になり、人々の健康とアートなど創造的活動への参加度は相関性があることが研究で明らかになってきました。文化的環境の不平等があるのならば、健康を支える環境にも不平等があるということになります。私たちのプロジェクトでは、その不平等を解消していく方法を具体的に研究し開発しています。例えば「望まない孤独や孤立」は、その人がその人らしくクリエイティブにいられない状態です。この状態を個人の問題と捉えず社会の課題として、この状況を緩和し、さらに解消するきっかけをアートや文化が作れるのではないかと考えています。
私たちはこの「望まない孤独や孤立」に対して、アートや文化をベースとした非医療的な手法である「文化的処方」を用い解決しようと考えています。医療や福祉分野と連携し、テクノロジーを活用していくことで、人々がアートや文化活動にアクセスできるようにし、人と人、人と社会がつながる回路を増やしていきます。
文化的処方というアプローチ
「ああとも」の活動はイギリスの「クリエイティブヘルス(Creative Health/創造的健康)」や「ソーシャルプリスクライビング(Social Prescribing/社会的処方)」を参照しながらも、日本独自の高度な医療や福祉のシステムとつながり、美術館などの文化機関、医療福祉関係機関、自治体、市民団体、民間企業といった幅広い組織と連携しながら、地域の文化資源が持つ力を、市民が主体的に社会へとアクセスするための回路を増やすために活用していきます。

ミュージアムの新しい役割
私たちはミュージアムにあるコレクションや地域の文化資源と、テクノロジーを掛け合わせ、新しい場所を創造し「つながり」をもたらすコミュニケーションを育みたいと考えています。これは自治体や医療・福祉の領域と市民と協働し進めていきます。
かつては「宝物を見せてあげる場所」だったミュージアムのシステムは、社会の変化の中で変わってきています。特に2000年以降、さらにコロナ禍を経た今ではミュージアムの存在は、人々が気軽に意見を交換し、新しい視点をシェアし、社会課題を再発見したしながら他者とのつながりを育み、さらにはソーシャルチェンジの場としての機能が期待されるようになっています。もう、ミュージアムは宝物を見るだけの場所ではないのです。
いま、ああともが考えていること
対話を重ねてアートを鑑賞する
さまざまな作品や文化リソースを「対話」しながら楽しむ場を作ります。正解のない問いを持った作品などが媒介となって新たなコミュニケーションの場となり、人と人の繋がりが生まれます。

移動式ミュージアム
ミュージアムが近くにない……。体や心の調子が良くない……。ミュージアムに行きたくても行けない理由は様々です。でもそんな時に、ミュージアムの方があなたのそばにやってきてくれたらいいかも?未来の移動式ミュージアムの形を模索していきます。

ミュージアムツールの開発
現代の様々なテクノロジーは、ミュージアムのコレクションや文化資源との新たな関わり方や楽しみ方をもたらしてくれるかもしれません。ツールを通して、地域の繋がりやコミュニティも。
文化リンクワーカーの学びの場づくり
アートや文化をベースにした活動を通して、人と人、人と社会をつなげる「文化リンクワーカー」。「文化的処方」の広がりを支える重要な存在です。この「文化リンクワーカー」の学びの場作りにも取り組みます。
運営体制
「ああとも」の運営の中心は、国立アートリサーチセンターのラーニンググループと東京藝術大学の桐山孝司研究室の合同チームです。そしてこの合同チームを中心に、様々な地域の自治体、医療や福祉の団体、アート・コミュニケータ等が連携します。
アート、テクノロジー、ミュージアムの領域において、様々な専門性とバックグラウンドを持ったメンバーが協働し、アートを通じたウェルビーイングな社会のデザインを共創していきます。
プロジェクト名について

本プロジェクトの名称は「Art & Wellbeing ああとも」です。
名前には、「アートと共にある生活」や「アートと友だちになる」という意味が込められています。さらに、仲間への呼びかけである(あぁ友よ!)という思いも含まれています。
「Art & Wellbeing ああとも」の愛称は「ああとも」、ウェブメディアの名称は「ああともTODAY」です。
ウェルビーイングな社会を実現する
ミュージアムにあるものは、私たち人間にとって普遍的価値があるという理由で保存しています。「ああとも」は、それらの作品を現在の時代に生きている人たちと、もう一度「文化的処方」という観点と共にシェアしようと考えています。その行為によって、私たちが今を生きることの、存在感や普遍的な価値を、認識し直すことができるのではないかと考えています。私たちはミュージアムや所蔵されている作品や資料には人間を肯定的に捉える大きな力があると思っています。「文化的処方」は、心身ともに満たされた状態であるウェルビーイングな社会を作っていく力があると信じています。
このような場所を創造することで、望まない孤独や孤立の状態におかれることなく、誰もが尊厳ある世界を生きられる社会の実現を目指そうと考えています。
プロジェクトメンバー

国立アートリサーチセンター ラーニンググループと
東京藝術大学 桐山孝司研究室の合同チーム
Photo: SAITO Yumi, TAKAHASHI Munemasa
「Art & Wellbeing ああとも」とは、東京藝術大学を拠点に、大学、国立美術館などミュージアム、地方自治体、民間企業など産官学の39組織(2024年5月現在)が連携する「JST COI-NEXT共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点(別ウィンドウで開く)」事業の中で運営されているプロジェクトです。
この「Art & Wellbeing ああとも」で、私たちはミュージアムにあるコレクションや地域の文化資源と、テクノロジーを掛け合わせ、新しい場所を創造しようと考えています。これは自治体や医療・福祉の領域と協働し、アートを軸としたコミュニケーションの場です。このような場所を創造することで、望まない孤独や社会的孤立におかれることなく、誰もが尊厳ある世界を生きられる社会の実現を目指そうと考えています。
「Art & Wellbeing ああとも」の運営の中心は、国立アートリサーチセンターのラーニンググループと東京藝術大学の桐山孝司研究室の合同チームです。そしてこの合同チームを中心に、様々な地域の自治体、医療や福祉の団体、アート・コミュニケータ等が連携します。
アート、テクノロジー、ミュージアムの領域において、様々な専門性とバックグラウンドを持ったメンバーが協働し、アートを通じたウェルビーイングな社会のデザインを共創していきます。
稲庭彩和子 桐山孝司
※この事業は、JST 共創の場形成支援プログラムJPMJPF2105の支援を受けたものです。
-

稲庭彩和子/INANIWA Sawako
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター主任研究員。University College LondonにてMuseum Studiesを修了。東京都美術館など公立美術館で約20年学芸員として活動した後、2022年より国立アートリサーチセンターに勤務。共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点の研究課題1リーダーとして文化的処方の企画開発を担当。「作品と人々との出会いの調整役」が主な仕事。アートは人の根源的な感覚を思い出させるなど、ケアの要素を持っていると考えており、自身のケアとしては料理も大切にしている。アートが健康やケアに良い影響を与えることを研究し広めたいと考えている。
-
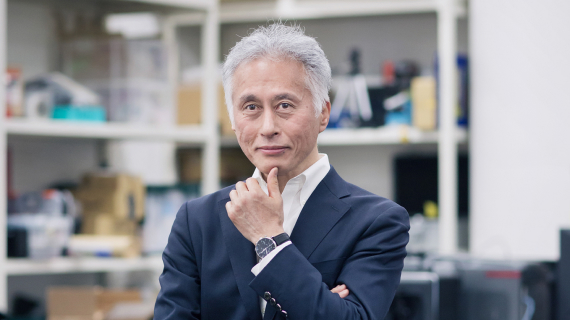
桐山孝司/KIRIYAMA Takashi
東京藝術大学大学院映像研究科研究科長、メディア映像専攻教授。共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点研究課題3リーダーとして、文化的処方を支えるテクノロジーの研究開発を行っている。「音と光の動物園」やヴィヴァルディ「四季」ライブアニメーションコンサートなど、研究から派生して定番となりつつあるイベントも行なっている。アートとケアという2つの言葉の共通部分があることを興味深く思い、日々の暮らしでは自分の手を動かすことを大事にしている。文化的処方については、今の社会での必要性を感じている。
-
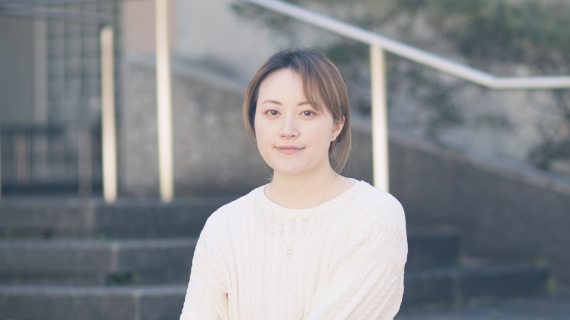
上平晃代/UEHIRA Teruyo
東京藝術大学共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点特任講師。人に反応する動物のアニメーション作品の制作・展示を手がけるアーティスト。日々の暮らしでは自分のなかのモヤモヤやグルグルの感情と向き合うことを大切にしており、愛用のChatGPT「Gぴょん」に思いの丈を打ち明けて、話を聞いてもらうのが日課。文化的処方については「おしごと」が第一に来るものの、「あまり難しく考えず、みんなそれぞれちょっとずつ心が豊かになれればいいなあ」という想いで活動している。
-

牧野杏里/MAKINO Anri
東京藝術大学共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点特任研究員。東京藝術大学大学院で建築設計を学んだ後、University College LondonでUrban Regenerationを修了、京都市で12年間市民主体のまちづくりに従事した。現在は文化的処方の構想立案・実施に向けて、文化施設・資源と共創する自治体連携プロジェクトや海外連携事業を担当している。アートを「感情、感性、感覚」として捉え、ケアを「助けるつもりがなくとも誰かの助けになり、支えるつもりが支えられている」相互性のある営みとして理解している。日常の中の感動を大切にしながら、感情や感性が誰かの支えになりうる社会の仕組みづくりを目指している。
-

増山透/MASUYAMA Toru
東京藝術大学共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点特任研究員。フリーランスで映像作家として活動しており、共創拠点では主に映像展示関係のテクニカル業務を担当している。アートやケアという言葉には、どちらも難解な印象があると感じている一方で、文化的処方については「自分にとっては当たり前の概念ではあったので、改めてそれが言語化されているような印象を持った」と語る。映像制作の現場で培った技術的専門性を活かしながら、アートとケアの融合を支える重要な役割を果たしている。日々の暮らしでは「何事も、思い通りにいかない領域があるという事を、忘れないようにしている」ことを大切にしている。
-

横山知保/YOKOYAMA Chiho
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター ラーニンググループ研究補佐員。武蔵野美術大学大学院修了後、広告企業、美術・デザインの教育業を経て現職。アートとケアについては、一つの感覚に限定せず五感を通じた体験が豊かな感情を育み、ミュージアムでの体験が自分らしく生きるヒントになると考えている。文化的処方を「地域の文化資源とひととのつながりを醸成する仕組み」として捉えている。自身のケアとしては、機嫌よく暮らすことを大切にし、多彩な文化体験を自分のためのご褒美として用意している。
関連ページのリンクはこちら
ああともTODAY 編集部
| 企画・編集・運営 |
稲庭彩和子(国立アートリサーチセンター) 井上英樹(MONKEYWORKS) |
|---|
ああともTODAY制作
| アートディレクション | 坂田佐武郎(Neki Inc.) |
|---|---|
| デザイン | 西宮悠(Neki Inc.) |
| イラストレーション | サンダースタジオ |
| ああともロゴデザイン | 株式会社ツートン |
| ウェブサイト構築 | 山崎哲由(SUBTONIC) |
発行
Art & Wellbeing ああとも
(国立アートリサーチセンター × 東京藝術大学)