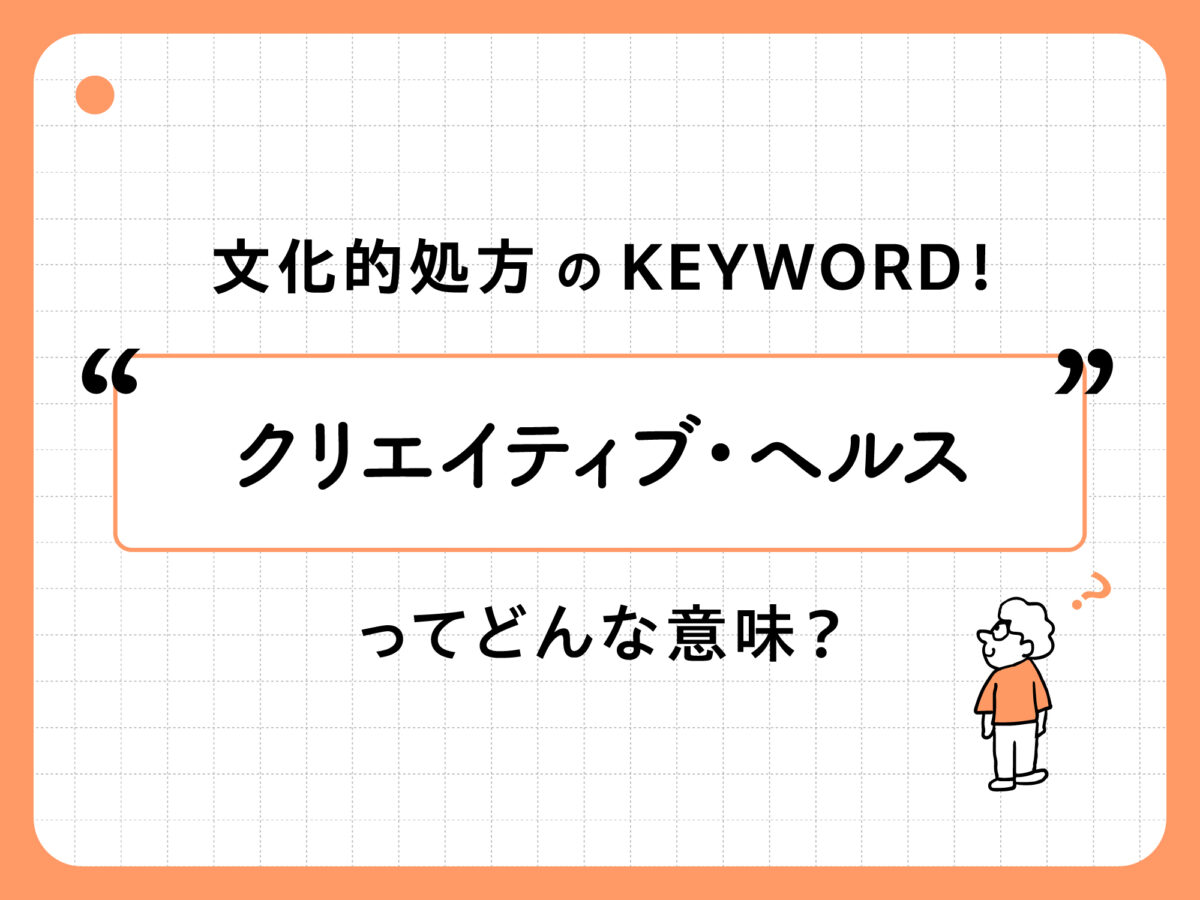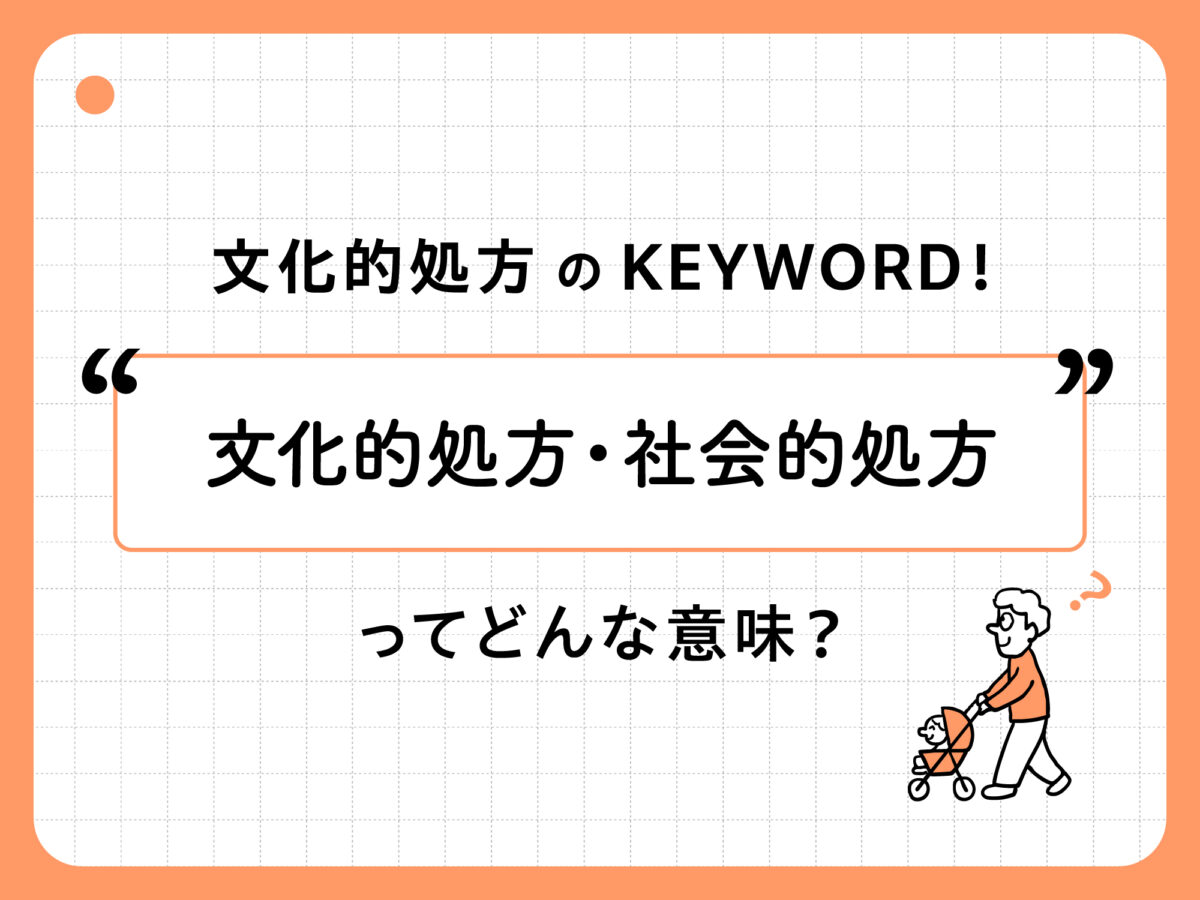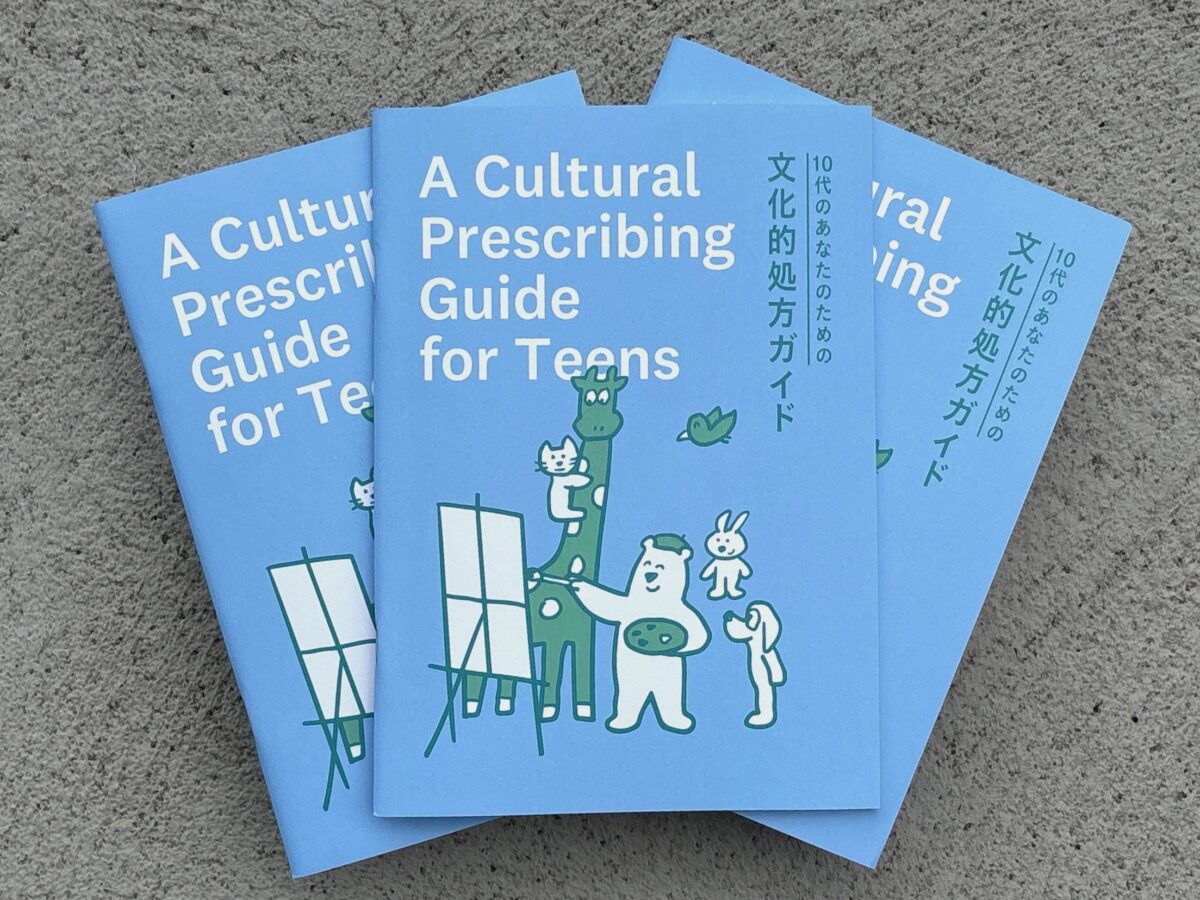人々の健康とウェルビーイングに、創造的なアプローチや活動で取り組む「クリエイティブ・ヘルス」。イギリス・マンチェスター都市圏では、医療・健康の格差に対し、「クリエイティブ・ヘルス」と呼ばれるアプローチを推し進めています。マンチェスター都市圏でクリエイティブ・ヘルス戦略を主導するジュリー・マッカーシーさんに、国立アートリサーチセンター主任研究員の稲庭彩和子が話を聞きました。 前編に続き、後編をお送りします。

前編からの続きです。
じわり広がるアートの力
稲庭 クリエイティブ・ヘルス戦略が策定されていったことで、マンチェスターに住む人々は「この地域ではクリエイティブ・ヘルスの取り組みをしていて、自分のウェルビーイングに作用している」、といった認識は広がってきているのでしょうか。一般の市民の方々の反応や受け止め方について、どのような印象をお持ちですか?
マッカーシー 人々がクリエイティブ・ヘルスを認知しているか、という問いであれば、「いいえ」という答えになります。まだ比較的新しい用語ですし、それを実際に人々に届けることもまだ始めたばかりだからです。現在、大きく5つのプログラムを実施していますが、マンチェスター都市圏で普通に歩いている人に「クリエイティブ・ヘルスとは何ですか」と聞いても、おそらく答えられないと思いますね。
ただ、これはそこまで悪いこととは思っていません。「定義を知っている」ことが大切なのではなく、人々が適切なサポートを望む場所、タイミングで効果的に受けられることが重要なのですから。同時に、例えばスポーツのキャンペーンのように、人々の健康意識を高めるための「クリエイティブ・ヘルス」についての広報活動は必要で、これは今後数年間の戦略の中心になると考えています。個人的に今大切だと思っているのは、人々に健康とは単に医者に行くことではなく、自ら家庭で、あるいは自分の家族や近所の人たちと健康的な行動様式を取り入れることで実現に近づけられる、自分の手でコントロールできるもので、それをサポートする活動の一つに創造性がある、そう知ってもらう手助けをすることです。身体的な運動が健康とウェルビーイングに直結するというのは大半の人が認識していると思いますが、同じようにクリエイティブ・ヘルスの概念を多くの人がだんだんと理解できるようになるでしょう。
病気を診る医療から健康をつくる医療へ

稲庭 とても重要な点ですね。社会的処方やクリエイティブ・ヘルスというのは、全人的なケア(体だけでなく、心のケアや社会とのつながり、生きがいなど、人間をまるごと大切にするケアの方法)の一つの方法だと思うのですが、そのケアの方法がお医者さんに行って薬をもらうという対処療法的な一つの方法だけではなくて、人間らしい暮らしの本質的なところにタッチしながらケアを進めていくという、人間とは何かを考えさせられるようなアプローチだと思います。
マッカーシー おっしゃるとおりですね。
稲庭 しかし、クリエイティブ・ヘルスが提案する医療や福祉のアプローチは、従来の近代医療の、病気になったらお医者さんに行って、薬をもらう、というシステムに慣れた人にとっては、なかなか理解しにくい面があると思います。そういう場面に対してマッカーシーさんはどのように、まだその効果を感じていない人々に説明をしているのでしょうか。
マッカーシー 私たちが発信しているのは、決して「お医者さんに行くべきではない」「薬を飲むべきではない」というメッセージではありません。一人ひとりの状況の中で一番よい生活を送るうえで、「ほかにもできることもある」ということをクリエイティブ・ヘルスでは伝えようとしています。先ほど社会的処方という言葉が出ましたが、例えばARCセンター(Arts For Recovery in the Community)では、アートに関する10週間のプログラム『Arts for Wellbeing(アート・フォー・ウェルビーイング)』があって、これをお医者さんが処方することができるんです。
リンク:https://arc-centre.org/adult-wellbeing-programmes/
例えば、うつや孤独を感じている人に対して、このプログラムへの参加を処方するのです。他にも処方なしで参加できるプログラムがあり、このような形で患者や潜在的な患者だけでなく、この効果を認識している医師や医療スタッフにも参加してもらったり、情報を共有したりしています。

もう一つの例として、イングリッシュ・ナショナル・オペラ(ENO)がコロナ禍にLong COVID(新型コロナウイルスの後遺症の一つ)を持った人たち向けのプログラムを開発しました。現在もCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者をサポートするため、医療従事者と共にこのプログラムを進化させていて、マンチェスター都市圏でもこれをパイロットプログラムとして取り入れています。このプログラムは医療行為として処方され、長期的に疾患がある人向けのものです。COPDの患者は身体的な症状だけでなく、孤独を感じることも多いのです。このような様々な要素に対して、プログラムが彼らの日常的なウェルビーイングと呼吸器の状態の双方にどのような効果をもたらすかを検証しています。
これらを踏まえ、最後に伝えたいことが、クリエイティブ・ヘルスの効果への理解をつくっていくためには、当然このような戦略の採算性の側面について説明する必要もでてきます。現在、医療経済の専門家(ヘルスエコノミスト)と共に、これらのプログラムの費用対効果を分析しています。過去の患者データが既に存在するので、例えば受診回数や救急車の利用回数などを比較することが可能です。それを基に、こういったアプローチへの資金の投入が医療サービスへの負担軽減につながる可能性がある、と示すことができるようになります。ただ、ある人の病気が、考えうる最悪の状況より軽くなった、ということの経済的効果を測定することはとても難しい課題です。
仲間と共に育てる−小さな種から大きな活動へ

稲庭 マッカーシーさん、ところで、クリエイティブ・ヘルスのプログラムの開発は、どのようなことから始まることが多いのでしょうか。たとえば、課題からプログラムを考えるのか、プログラムがあって課題と結びつけるのか、など。
マッカーシー すべてはパートナーシップから始まります。対話を通じて課題を認識し、それに対するアプローチや可能性を探ります。課題を共に探求するところから始まって、時には「今やるべきではない」「このアプローチではうまくいかない」という結論に至ることもあります。多くの場合、課題と、それに対する解決方法を共に探求すること、その両方から始まるのです。
稲庭 そのパートナーシップを選ぶこと自体重要ですよね。共同で実施する際の見極めはどのように行っているのですか?
マッカーシー パートナー選定の最大の基準は、医療の不平等がどこにあるかという点と、クリエイティブ・ヘルスの手法が実際にどれだけ活用できるかという点です。
具体例を挙げると、未就学児向けのプログラムをマンチェスター都市圏の広域自治体と医療組織(NHS GM)で開発した時の話です。Ballet Rambertという全国規模のダンス団体から、共にやりたいという声がけがありました。そしてすぐに、彼らの未就学児向けのプログラムが、保育施設の子供たちの運動能力を伸ばすうえで、その施設スタッフの研修プログラムのベースとして生かすことができると認識しました。小規模なパイロットプログラムを経て、共同作業をするうえでの色々な学びを得て、これは効果的だ、と共に理解しました。実際に保育施設で働いている人たちやたち、パートナーにとって有益であり、コスト面でも効果的だ、そう理解できたので、プログラムをスケールアップしていきました。これはある種のアクションリサーチ(実践と研究の循環プロセス)として成長していったのです。
パートナーシップや対話は有機的に発展していくものであり、最初は小規模に始めて、うまくいくことをステージごとに確認しながら拡大していくというアプローチを取っています。現在実施している五つのプログラムも、こうしたプロセスを経て発展してきました。
「あったらいいね」から「ないと困る」へ
稲庭 最後の質問です。マッカーシーさんはどのようなゴールを描いていますか?
マッカーシー 目標はクリエイティブ・ヘルスを持続可能なものにすることです。クリエイティブ・ヘルスが有機的な医療の中に組み込まれ、最終的に人々が自分たちのウェルビーイングにとってそれが重要であるという共通認識を持ち、必要な時、欲しいと思う時にすぐアクセスできるようにすることだと思っています。
フットボールをしたい人にクリエイティブ・ヘルスを押し付けることはできませんが、もしその人が創造性を通じ健康になりたい、となったらすぐにその人がそういった機会にアクセスできる環境を整えたいのです。それは地元の、自分が住んでいる地域の隣人が提供しているかもしれませんし、医師から提案されるケアプランの一部かもしれません。必要になった時、欲しいと思った時に利用できる状態にすることが最終的な目標ですね。
私たちがよく使うフレーズに「from nice to have to need to have(あったらいいねから、ないと困るへ)」というものがあります。クリエイティブ・ヘルスを「あったらいい」というレベルから「ないと困る!」というレベルに引き上げることを目指しています。
このフレーズは医療従事者やコミュニティに対しても言えることです。例えば医師が「文化的なものがあってもいいかもね」と考えるレベルから、「これは本当に必要なものだ」と認識するレベルに引き上げることが重要なのです。あるいはコミュニティのレベルで、住民自らの健康とウェルビーイングをサポートする創造的な活動に、誰しもがアクセスができるようになっていてほしい。そのような世界を私たちは目指しています。