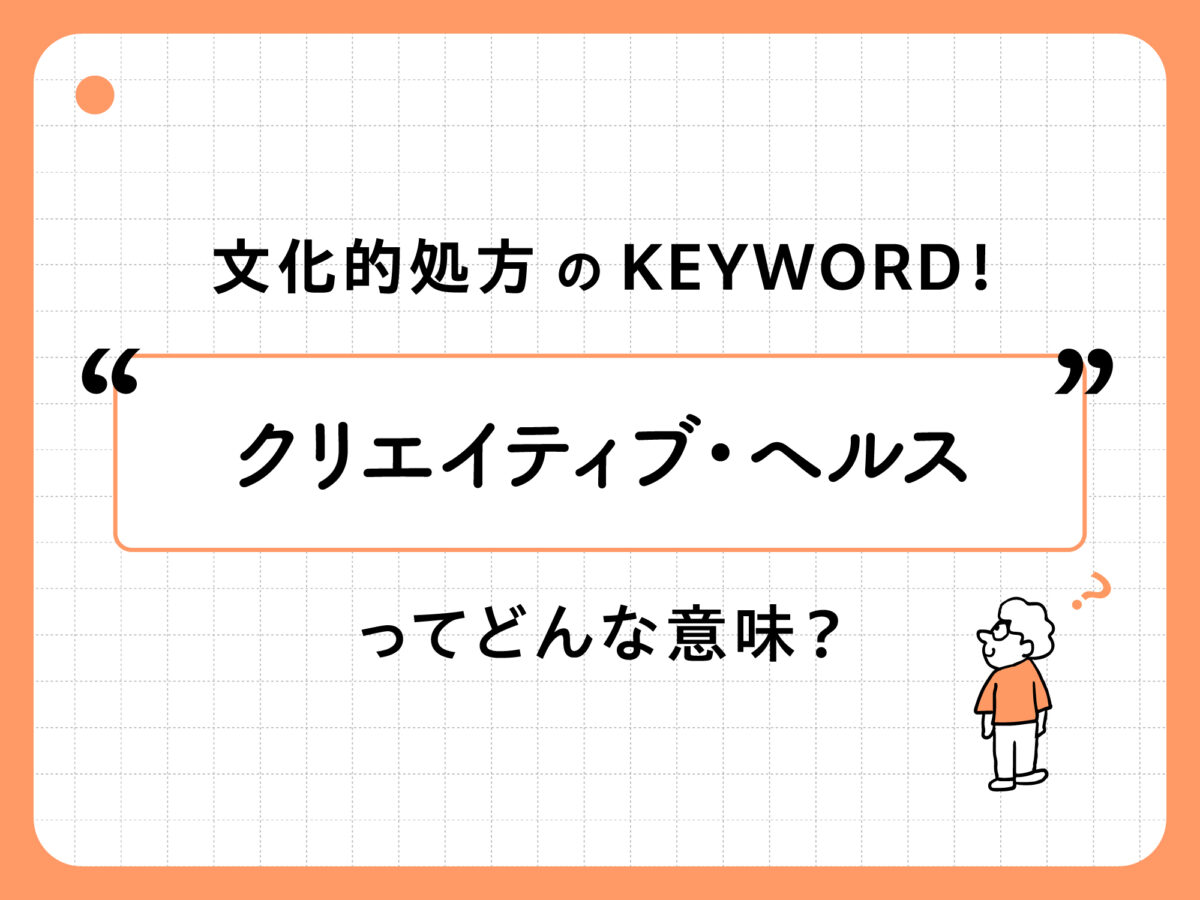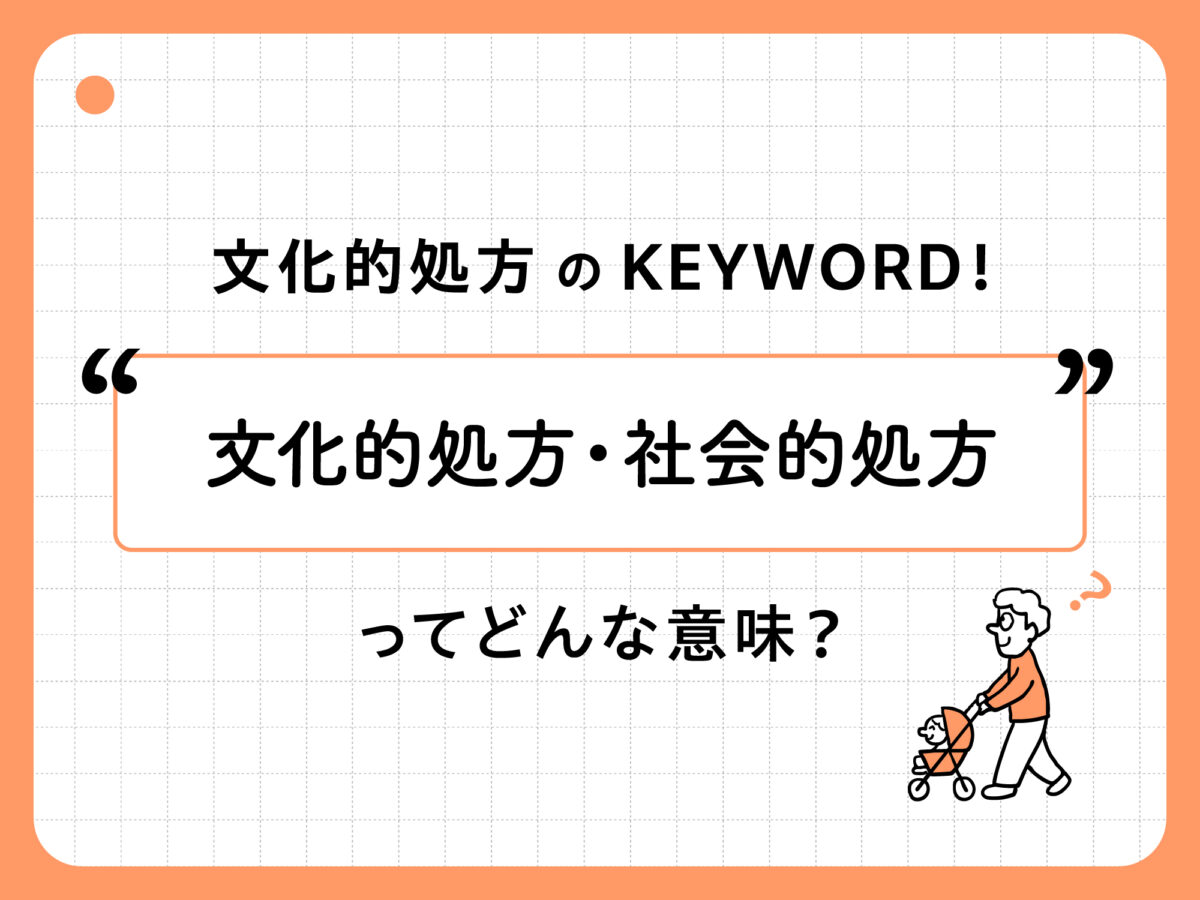研究開発課題リーダーとして、稲庭彩和子(国立アートリサーチセンター)とともに「ああとも」を率いる桐山孝司(東京藝術大学東京藝術大学大学院映像研究科長)。「ああとも」の活動にかける思いとは?
人はものづくりをしながら、問題も生み出した

私は工学部の出身で、大学院ではAI(人工知能)を設計支援に応用する研究に携わっていました。その後1992年に東京大学人工物工学研究センター (RACE)ができ、そこに参加することになりました。RACEは人類の持続可能性に資する次世代ものづくりに関する研究機関です。当時はバブル時代を経て、大量生産をし続ければ生活や社会がよくなるというパラダイムが限界になってきたと考える人が増えていました。人工物工学を提唱した吉川弘之先生(元、東京大学総長)は現代の邪悪なるものという言い方で、かつて外敵を防ぐために高度化した人工環境が、いつのまにか経済格差や災害の大規模化など、人間への脅威を内側から生じさせていることを指摘していました。人工環境は人間によって設計されたものであり、設計行為というものをよくわかっていないことに現代の課題の原因を見ていた、といえます。
当時から現代の邪悪なるものの一つに、孤立・孤独の問題も挙げられていました。人が社会で孤立し、孤独になるような環境を作ってきたのは人間自身です。私たちはものづくりをしながら、様々な問題も生み出してしまっていたのです。そのような問題の解決は、細分化された学問では到底太刀打ちできないという認識から、ものづくりの現場のように総合的、横断的にものごとを見ようという発想でRACEは誕生しました。
工学分野から、東京藝大へ
当時のRACEでは、様々な発想を取り入れてオープンなかたちで設計をする環境を研究していました。そこでは有限設計ワークショップという授業の中で、IDEOというデザインカンパニーにプロトタイピングを実践してもらっていました。IDEOはスタンフォード大学から派生した、シリコンバレーを拠点にした会社です。私自身もRACEでの活動が一段落した1999年に、PBL(Project-Based Learning:問題解決型学習)を積極的に取り入れているスタンフォード大学の設計研究センターに移ることになりました。4年間をその研究所で過ごし、日本に戻った後、JSTのさきがけ研究員を経て、東京藝術大学で映像研究科メディア映像専攻の立ち上げに参加します。そこで佐藤雅彦先生と同僚になりました。私は工学出身でアーティストではありませんし、佐藤先生も広告のクリエイティブディレクターを経て、分かるということについて慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の研究室で実践をされてきた方ですので、東京藝大という環境のなかでは畑違いでした。しかしここで、試作を繰り返しながら現場で考えるという問題解決型学習がとても役立ちました。広いスタジオや工作室があったこともあり、時間をかけて試作と改良をしながら展示物を作ることができました。
テクノロジーがアーティストの表現を支える
2人でユークリッド(Euclid)を結成し、《計算の庭》(2007年)や《指紋の池》(2010年)という映像やテクノロジーを使用した展示物を制作しました。《指紋の池》では、池に見立てたディスプレイの前にあるセンサーで指紋をスキャンすると、画面の中を指紋が魚のように泳ぎ出します。しばらくすると、指紋は群れに紛れて行方がわからなくなるのですが、再度センサーに指を置くと群れの中から自分の指紋が現れ、指に戻ってきます。人は自分の指紋に興味なんてなかったのに、自分の指紋が戻ってくると愛着を持てるようになる。これはアニメーションの力ですが、この動きに対する興味や湧き出る感情は、人間の本能に結びついたことのように思いました。

アニメーションと音楽では、2017年に当時の澤和樹学長が発案し、映像研究科の岡本美津子先生がプロデュース、山村浩二先生が監修をした、ヴィヴァルディ「四季」アニメーションプロジェクトに参加しました。「四季」は春夏秋冬からなる4つの楽章からなり、ソネットという短い詩がついています。それぞれの楽章とソネットからイメージするアニメーションを、アンナ・ブダノヴァ(ロシア)、プリート&オルガ・パルン(エストニア)、和田淳(日本)、テオドル・ウシェフ(ブルガリア)に描いてもらいました。2017年の響ホールでの初演では、そのアニメーションを手動で生演奏に同期させて投影しました。ただその作業は非常に集中力が必要で、練習に時間もかかったので、2018年に一年間かけてヤマハと共同研究し、AIによって映像を音楽に同期させるAI映像同期上映システムを開発しました。あくまで演奏家が主体となって音楽を組み立て、そこに映像がそれに合わせていくことで、音楽と映像がぴったり同期する気持ちよさも感じてもらうことができるようになりました。さらに映像の上映に必要な労力も大幅に減らすことができて、2019年1月のロサンゼルスのアラタニシアターでの公演以来、国内外のコンサートで披露できるようになりました。私自身、工学出身の人間ですので、私にできることはアーティストたちの能力と社会との関係を繋げる環境作りをしたり、技術で支援したりすることだと思っています。今後、この分野はAIがさらなる力を発揮することでしょうね。
現場で考え、テクノロジーを生む

共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点が本格型としてスタートし、研究開発課題1のリーダーである国立アートリサーチセンター(NCAR)の稲庭彩和子さんから、私の担当する研究開発課題2(現在3)とともに、ネットワークやAIで対話型鑑賞をアップデートするプロジェクトを提示いただきました。私自身も技術を使ってなにか貢献できないかと思っていましたので、大変嬉しく思い参加することにしました。今後は、NCARや「ああとも」のみなさんと共生社会をつくる取り組みに参加していくわけですが、今考えているのはアートコミュニケータ(アートを介してコミュニケーションを生み出していく人)の教育にAIが役に立つ仕組みです。例えば、アートコミュニケータが対話型鑑賞を行う際、一つの観点を示すことがあると思います。そこでストックされている過去の対話型鑑賞のログを基に、AIが話題やヒントを提案してくれるというものです。新人コミュニケータの教育的な目的など、いろんなことができると思います。
しかし、テクノロジーの新しさだけを先行させることは適切でないと考えています。テクノロジーで驚かすものは長続きしません。できればテクノロジーは表に出なくて、体験の中身を持ち帰ってもらうことが何より必要なことです。そして重要なのが、現場を持っていることです。NCARの皆さんの発想や考え方は、常に現場を念頭に捉えているように思います。この「ああとも」チームでも、常に現場で生きる技術を作っていきたいと思っています。