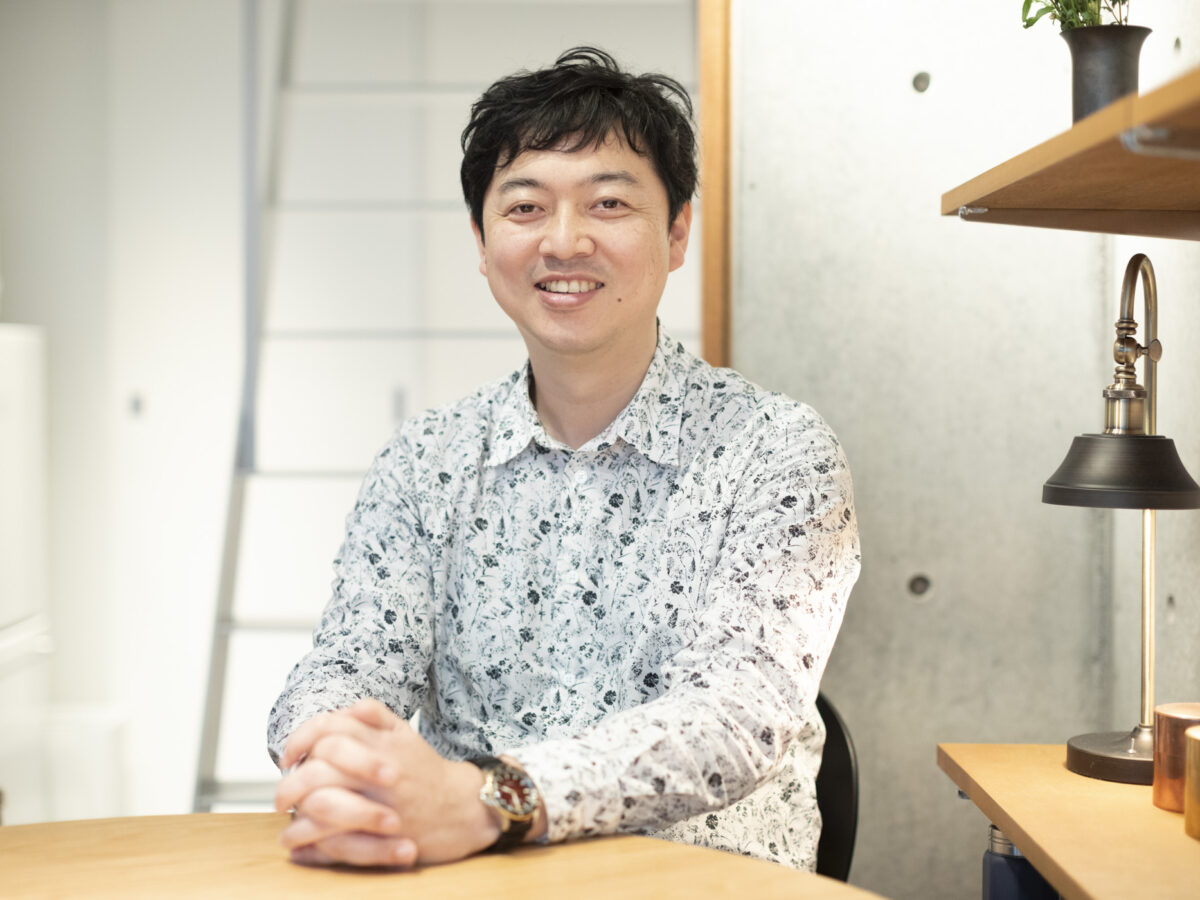広がりを見せる社会的処方という言葉
最近、「社会的処方」という言葉がじわじわと広がりを見せています。ただ、この言葉に初めて触れる方の中には、「処方というからには何か専門的なことかもしれない。私には関係ないかも」と思うかもしれません。事実、『社会的処方』『みんなの社会的処方』の編著者である西 智弘さんは、川崎市の病院で患者さんと向き合いながら、地域活動にも力を注いでいる医師です。やはり、社会的処方は医師や専門家だけのものでしょうか。しかし、この本を読めば、その答えが「NO」であることが明らかになります。社会的処方とは「薬を処方することで患者さんの問題を解決するのではなく、『地域とのつながり』を処方することで問題を解決するというもの」と、西さんははっきりと書いているのです。
市民一人ひとりの特技が誰かの「薬」になる
少し社会的処方について考えてみましょう。たとえば、心や身体の具合が悪くなったとします。病院に行くと、たいていの場合は「この薬を飲んでくださいね」と処方箋を渡されます。この時、薬以外にも体操や音楽、アートなど地域のサークル活動を紹介されたらどうでしょうか。つまり、社会とのつながりを処方されるのです。
イギリスでは釣りや編み物などの集まりに参加した高齢者がうつ病から脱したなどの例があるそうです。この社会的処方を実践する際に中心となるのが「リンクワーカー」という存在です。イギリスではリンクワーカーが患者さんの生活や興味についてヒアリングし、地域資源(釣りやアートや園芸など)とマッチングしてくれます。
「本当にそんなことで状況が改善するのだろうか」と思う人もいるでしょう。ですが、医療機関に持ち込まれる問題の2~3割は社会的な問題と言われています。社会的処方は市民一人ひとりの活動や特技が誰かの「薬」になる可能性があるのです。『社会的処方』『みんなの社会的処方』には、社会的処方が生まれた経緯や社会的背景などが紹介されています。なかでも、自分事にできるのが国内外の社会的処方の実例です。
・言葉ではなくアートで対話をする「Drawing Life」(イギリス)
・相談や対話ができる場所「暮らしの保健室」(日本)
・高齢者と学生が共に暮らす下宿「京都ソリデール」(日本)
・誰もがリンクワーカーになれる街「フルーム」(イギリス)

などなど、社会的処方のタネが盛りだくさんです。本に登場する人たちは万能なスーパーマンではなく、普通の市井の人々です。誰かが困っていたら、なんとかしたい。そんな“良識的なおせっかい”の気持ちを持つ人たち集まり、互いにネットワーク化し、社会からの孤立や孤独を阻んでいます。
本を読み進めるうち、「自分ならこんなことができるかも」「あの人に頼めばこんなことができるかもしれない」と、考えが止まらなくなるはずです。おそらくそれが、本書の狙いのひとつでしょう。ぜひ、『社会的処方』『みんなの社会的処方』の2冊を手に取り、自分に何ができるかを考え、周りから実践してみてはいかがでしょうか。