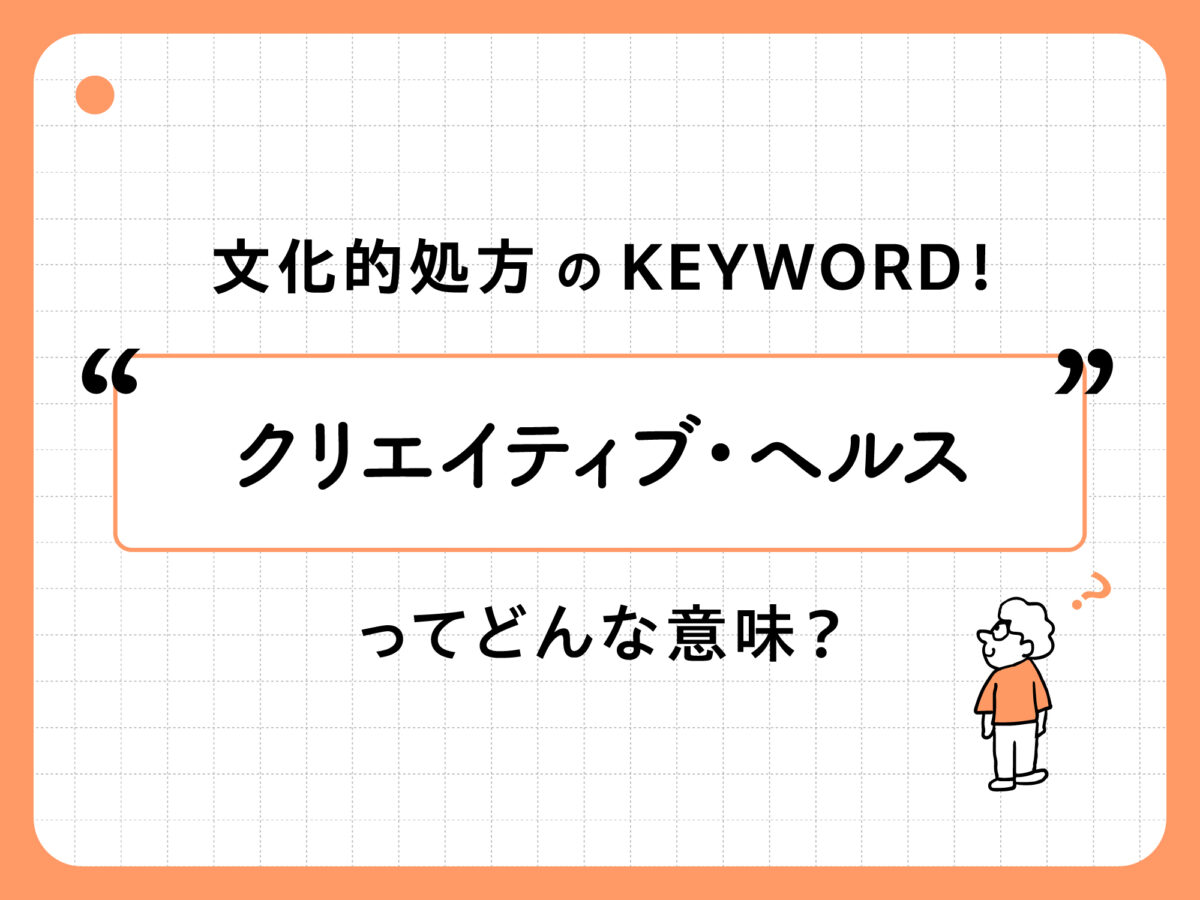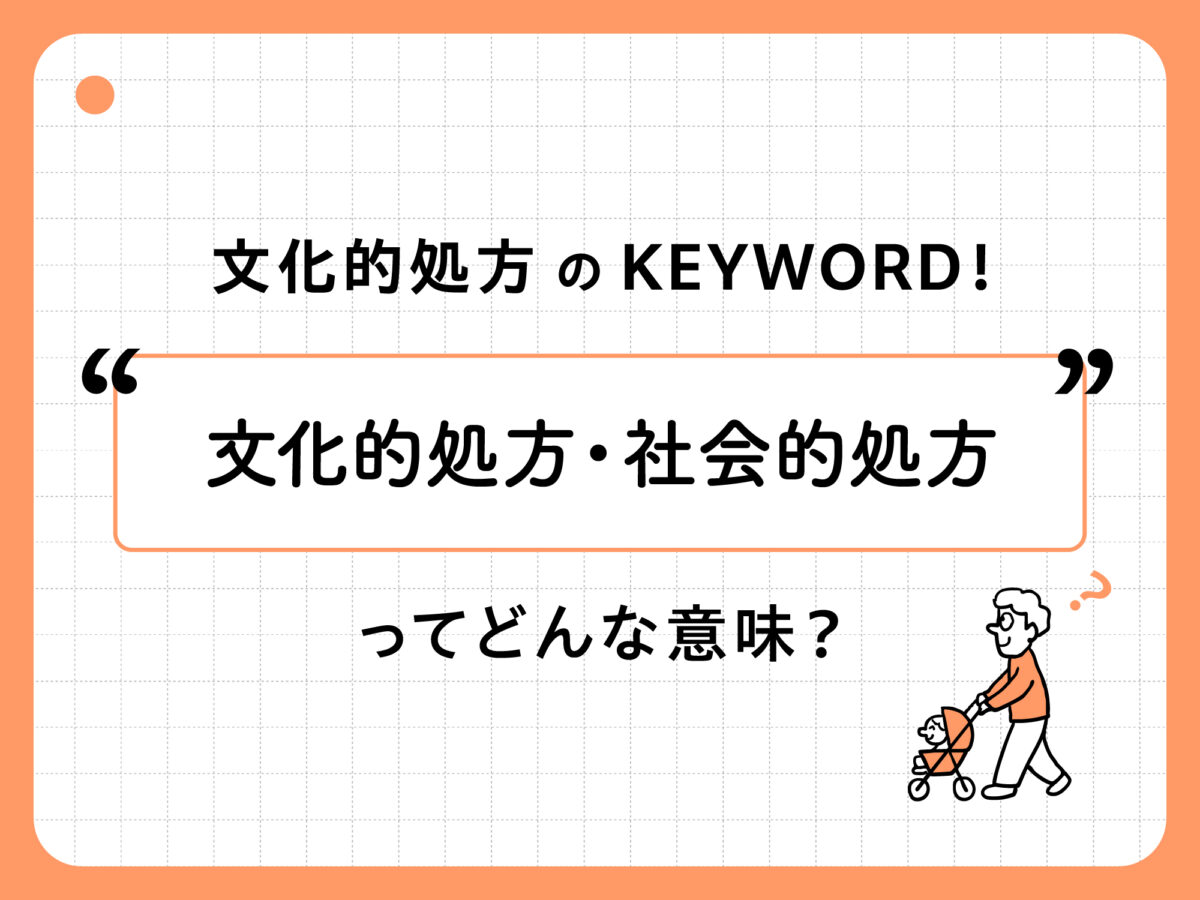『社会的処方』『みんなの社会的処方』(学芸出版社)という本を出版し、実際に川崎市に誰もがアクセスでき、相談をすることができる「暮らしの保健室」を運営する医師の西 智弘先生。川崎市の「暮らしの保健室」で西先生にアートと社会的処方の関係について尋ねました。
もっと気楽なつながりを持とう
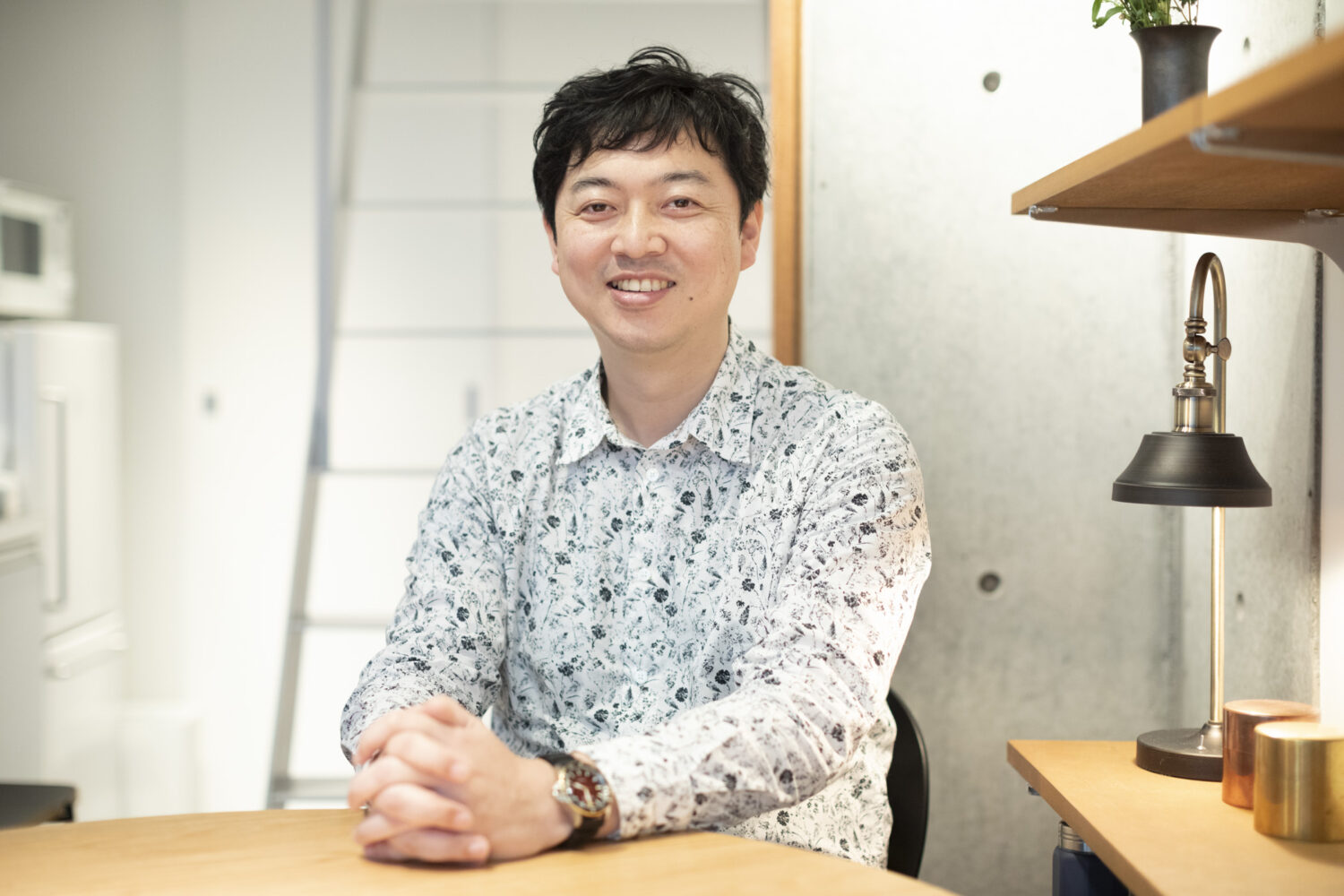
アートの前では誰もがフラットになれる
編集部 西先生の『社会的処方』『みんなの社会的処方』には、社会的処方の実例がたくさん紹介されていました。その中でもアートとの関わりに関する多くの事例が紹介されています。西先生はアートと社会的処方の可能性や関係について、どのようにお考えですか?
西 アートの前では誰もがフラットになると思います。アートに向き合う過程において社会的地位、貧富の差、年齢、障害や病気の有無などは関係ありません。また、アートを鑑賞する人たちとの間に対話が生まれることがあります。このアートをどう見たか、どんな印象を受けたか、なぜそう感じたのかを話し合い、考えます。これがすごく良いことだと思うんですよ。それぞれの解釈が出てくることは、それぞれが持つ独自の視点や背景を認め合うことにつながります。アートは多様性を受け入れる手助けをしてくれると思います。

例えば、『社会的処方』に登場するパトリックさんは、ヘイスティング(イギリス)にあるDrawing Lifeという団体でプロジェクトを行っています。この団体は認知症とともに生きる人々と介護者が経験する孤立感を和らげることを目的としているんです。『社会的処方』で紹介したプログラムでは認知症患者やその家族を対象にデッサン会を開いていました。福祉的な目的で絵を描かせているわけではなく、ナーシングホーム(日本の老人ホーム)で本物のモデルを使ったデッサンを行っています。彼がこの活動をしている理由は、認知症の人たちが自由に表現することに対して魅力を感じているからです。「こんな表現があるのか!」と、毎回新鮮な驚きがあるそうです。
私たちが「認知症の方を支援する」と考えたとき、「認知症だからこんなことはできないかな」「これはできるかな」と考えがちです。しかし、パトリックさんは「参加者を患者ではなくアーティストだと思っている」と言います。実際、アーティストとして接していく内に、話をしなかった人が話すようになったり、自らの表現を見つけることができたりするようです。こういうことができるのがアートの大きな力なんですね。
編集部 このような取り組みが日本でも行われるといいですね。同時に社会的処方の理解が不足していると、表面的なアプローチに終わってしまう恐れがありますね。
西 そうですね。例えば、塗り絵をさせて「いい絵が描けましたね、素晴らしいですね」というような答えが決まっているプログラムは本人らしさがでてこなくて、参加者にとって創造的で面白い体験とは言えないかもしれない。きれいに塗ることが重視されるのではなくて、ぐちゃぐちゃに引いた線に対しても、その線の動きの素晴らしさを見出せるような、その人らしい表現が認められるべきです。社会的処方という言葉が一人歩きをして、「支援者」と「被支援者」がいると考えてしまうと、そこに分断が生まれます。「支援してあげる」というふうになりがちなのがちょっと危ういですよね。
誰もが「ただの住民」として存在することの大切さ

編集部 分断を生まないために、どのようにすれば良いでしょうか?
西 そうですね。例えば私たち医療関係従事者は、病院内では支援する側の役割です。しかし、街中で同じように「支援する側」を強調して振る舞うのはよくないですね。街中で医療者として振る舞い、人々に「正しい医療とは何か?」を教えるようなことをすると、それがかえってコミュニティに分断を生んでしまう。私たちは、誰もが「ただの住民の一員」として存在することが大切だと思います。アーティストが「私はアートが得意です」と言うのと同じように、医者である私も「得意分野が医療や医学の知識である」であるわけです。全員が対等なんですね。障害のある人々、認知症の人、がん患者、子どもたち。すべての人が同じ関係性の中で存在しているわけですから。
社会的処方という言葉を意識しすぎると、孤立や孤独を解消しようと意気込み「支援者」として街に存在しようとする姿勢になりがちです。しかし、先にお話ししたように全員が対等であればいい。それほど肩肘を張る必要はないのです。もっと気楽に、みんなで楽しむべきですね。「こんな絵を描きました」と言われたら、「すごいですね、面白いですね!」と素直に楽しむべきです。それでいい。わくわくやっていけば良いだけの話なのに、正しいとか間違っているとかを言い出しては、つまらなくなってしまいます。
人と人をつなげるリンクワーカーという存在
編集部 『社会的処方』には日本ではまだ馴染みのないイギリスの「リンクワーカー(社会的処方をしたい医療者からの依頼を受けて、患者や家族に面会し、地域コミュニティグループとマッチングさせる立場)」という職種が紹介されていました。日本でも社会的処方を実践していく上でリンクワーカーの役割が重要になってくるのでしょうか?
西 確かに患者と社会資源をつなぐリンクワーカーの存在は重要です。ただ、イギリスの場合は20年以上も時間をかけて今の状況が生まれてきていて、現在は医療システムの制度として仕組み化されているんですよ。イギリス式のリンクワーカーは研修を受け、支援スキルを認定され、年に何度かのフォローアップを受けながら、その技術を維持します。日本にもイギリス式を導入しようという考えもありますが、孤立の問題がすでに表面化している日本の現状において、リンクワーカーの制度化を目指すことを優先していたら時間がかかりすぎて、今ある現状に対応が間に合いません。私がまず今できることとして日本で推奨したいのは、友だち同士のように趣味や地域の情報を交換する関係性を意識的に広げることです。
ある人が、望まない孤独の状況にある人をみて、これは何かしら社会のコミュニティと繋げた方がいいのではないかと感じたとします。その方との会話の中でバスケットボール好きだとわかったとしたら、「駅の近くにバスケットボールコートができたことを知っている? 子どもと一緒なら無料で使えるようだよ」というような会話が自然と生まれたらどうでしょう。友人同士のような会話のなかで、人と地域とのつながりを作ることができます。日常的な会話からも、社会的処方を進めていくことができます。日本式のリンクワーカーは、まず制度化するのではなく、リンクワーカーのコンセプトを理解した上で、心構えやスキルを広く共有し、できる人ができる範囲でやっていこうという考えです。
私は孤独・孤立問題に対する国の姿勢を明確化し、地方自治体、民間団体、企業、市民が連携して取り組む体制整備を目的とした『孤独・孤立対策推進法』はすごくいいと思っています。「今、自分は孤立してない」と思っていても、病気や事故、年を取ったことをきっかけになど、人は簡単に孤立してしまうことがあります。誰もがいずれ孤立する可能性があるわけです。今、孤立している人を何とかしないと、自らが孤立したときに誰も助けてくれなくなる。だから、孤立・孤独支援はみんなでやったほうがいいと思います。日本でイギリスのように専門化が進むと、肩書のある専門家以外が手を出しにくくなるかもしれない。それこそ、誰もが皆取り組むべき課題だとする法律の趣旨にも沿ってないと思うんですよね。

つながりの場としての「暮らしの保健室」の役割
編集部 西先生は「暮らしの保健室」(神奈川県川崎市)を運営されていますね。
西 ええ。暮らしの保健室は誰でも予約なしに、健康や介護や暮らしの中でのさまざまな困りごとの相談ができる場所です。人にはそれぞれつながりに適した場所があると思うんですね。例えば、カフェ、銭湯、美術館など、自分に合った場所から社会につながればいいと思いますね。実際にあった事例なのですが、あるお店のご主人が常連客から、重い病気で苦しんでいると聞いたんです。しかし、ご主人は医学の専門知識はなく、さらにとても繊細な方で、苦しみや痛みの話を聞くのがすごく苦手なんですね。常連さんだから話は聞くけれど、本当は極力そういう話は聞きたくない。このままだと話を聞くご主人が潰れてします。そこで、ご主人は「私には難しい話なので『暮らしの保健室』という場所があるから、そこで話をしたらいいのでは」と、「暮らしの保健室」と常連さんをつなげてくれたんです。ご主人は『暮らしの保健室』という場所がなければ、深刻な話に潰されていたかもとお話ししてくださいました。「私はあなたが困っていることに対し、直接解決できないけど、あなたのことを助けてくれそうな人を知っている」というネットワークが街の中に広がっていることが重要だと思いますね。
編集部 「暮らしの保健室」にはアート作品が飾られ、とても居心地のいい空間ですね。先生はアートがお好きなのですか?
西 昔はそれほど好きではなく、理解ができなかったんですよ(笑)。美術館で作品を見ても何がいいのかさっぱりわからなくて。だけど、数年前から写真を撮るようになり、その後に美術館へ行くと、絵の素晴らしさを感じられるようになりました。作品を見て写真表現と対比すると、写真では表現できないことが見えてきます。すると、それまでなにが良いかわからなかったアートが、面白くなってきたんですよね。海外の社会的処方の事例を勉強していると、アートが関連するプログラムの事例が山のように出てきます。そういうものを見るだけでも、発想や面白さに触れることができますね。だけど、アートと社会的処方を簡単につなげられるかというとそうでもない。例えば「写真表現を使った社会的処方」を考えるとします。撮った人と作品との対話から、「この場所は昔、こんなんでね」なんて、ヒストリーが出てくるかもしれない。だけど、カメラを持っていなければできないし、なければメーカーから借りる必要も出てくる。絵と比べると、ちょっと道具的なアクセスの問題が出てきます。

社会的処方でアートを介するときに考えなくてはいけないのが、このアクセスの問題です。「森の社会的処方(Green Social Prescribing)」や「水辺の社会的処方(Blue Social Prescribing)」という考え方があるのですが、森や水辺に行くのは良いけれど、森や山に行く移動手段やお金をどうするのか。足に障害のある人は砂浜をどのように移動するのかなど、そういう点も考えなければなりません。実は森や海辺もアクセスに関しては不平等ですよねという声が上がり、アクセスの不平等を解決していこうという概念が登場しています。
アートも同じです。アートに対するアクセスが悪いとしたら、それはアートが富裕層や健常者のためだけのものになっているかもしれない。私も含め、多くの人が「アクセシビリティ」を忘れがちです。美術館なんて誰でも行けるものと思っているかもしれないけれど、場所が離れていたり、観覧料を出すことが大変な人がいます。川崎市は「誰もが文化芸術を楽しめるまち」という意味を込め「アート・フォー・オール」という言い方をしています。アート・フォー・オールになるためには、まずはアートに接しやすくする「アクセシビリティ」を真剣に考えないといけませんね。
ですが、望まない孤立や孤独で困った人がいても、街の中にたくさんのつながりを持つ人が存在し、ネットワーク化していけば多くは解決できるでしょう。孤立という病は地域のつながりで治すことができます。ご自身でできる社会的処方について、みなさんが考えていただけたらと思います。